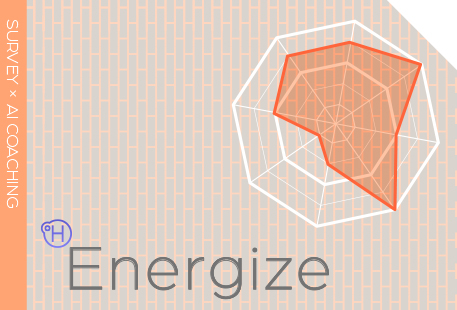AIの集団知性について本格的に語る前に、そもそも集団知性とは何なのか、どうやって生まれるのかを整理しておきたいと思います。皆さんは集団知性をどのように理解していますか?
私たちは「集団知性(集合知)」という言葉をよく耳にしますし、大勢の人が協力して作り上げた成果を目にして、その力を実感することもあります。しかし、人類の偉大な知的成果を集団知性の賜物だと言いながら、それが一体何なのか、どのような仕組みで生まれるのかを正確に説明するのは意外と難しいものです。
今回は、この集団知性を科学的に観察する道筋を示した画期的な研究をご紹介します。
出典
- Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. science, 330(6004), 686-688.
https://doi.org/10.1126/science.1193147
集団にも「知能」は存在するのか
Woolleyらの研究チームが注目したのは、個人に一般知能があるように、集団にも同様の知能が存在するかどうかという問題でした。
一般知能(g)というのは、さまざまな認知課題で共通して働く知的能力のことです。たとえば、音の高低を聞き分ける、色を区別する、数学問題を解くといった、一見無関係に思える課題でも、ある分野が得意な人は他の分野も得意という傾向があります。多くの研究で、この一般知能的要因が個人の課題遂行能力の3~50%を説明できることが分かっています。つまり、異なる領域の課題を統合的に処理する、何らかの一般的な知的能力が存在すると考えられているのです。
研究者たちは、この一般知能と同じ方法で、集団知能(c)の存在を証明しようと試みました。集団にさまざまな課題をやってもらい、その成績に共通して影響する要因、つまり集団としての一般的な知的能力が見つかるかどうかを調べたのです。

実験では、2~5人のグループを作り、多種多様な課題に取り組んでもらいました。課題は、集団作業を「協力 – 競争」と「認知 – 行動」という二つの軸で体系的に分類したMcGrathの枠組みに基づいて選ばれ、ブレインストーミング、視覚パズル、道徳的判断、限られた予算でのショッピング計画など、様々な領域にわたって実施されました。そして個人の一般知能と同じように、集団でも異なる課題に共通する一般的な知能(c)が観察できるかを分析したのです。
結果は驚くべきものでした。集団にも確かに一般的な知能が存在していたのです。この集団知能要因(c)は、グループの様々な課題パフォーマンスの約43~44%を説明しました。つまり、集団も個人と同じように、異なる領域の課題を統合的に処理する一般的な知的能力を持っているという証拠が得られたのです。
さらに興味深いのは、集団の課題遂行能力が、メンバー個人の知能と有意な関連性を示さなかったという点です。研究者たちは事前に個人の一般知能テストを実施し、メンバーの平均知能や最高知能が集団の成績と関連するかを調べましたが、有意な関係は見つかりませんでした。つまり、集団のパフォーマンスは、個人の知能とは別の何かによって決まっていたのです。
心を読み取る能力が鍵
では、集団の知的能力に影響を与えていたのは何だったのでしょうか?
研究チームは様々な要因を調べた結果、集団知能(c)とグループメンバの平均的な社会的敏感性の間に関連があることを発見しました。ここでいう社会的敏感性は、「Reading the mind in the eye」というテストで測定されました。これは、人の目の部分だけの写真を見せて、その人の感情を読み取る能力を測るテストです。他人の心の状態を察知し理解する能力を評価できる方法の一つです。
このような能力は、Mentalizingや Theory of Mind(ToM)と呼ばれています。この用語は元々チンパンジー研究で使われ始めたもので、他の個体にも自分と同じような心があると理解し、その心が行動を導くと考えることで相手の行動を予測しようとする過程を指しています。これは人間にも共通して見られる能力です。
なぜToM能力が集団知能と関係するのでしょうか?具体的なメカニズムを明らかにするには、さらなる研究が必要ですが、一つの可能性として次のようなことが考えられます。集団で課題を解決するには、メンバー一人ひとりの活動や思考を効果的に調整する過程が必要です。多様な人々の認知や活動、協力や競争を最適な答えに向けて統合するためには、お互いの心の状態を推測し、それに基づいて行動を調整することが重要な役割を果たすのではないでしょうか。
他にも興味深い発見がありました。グループ内での発言回数が均等に分散されているほど、また女性メンバーの割合が高いほど、集団知能(c)が高くなる傾向が見られたのです。特に注目すべきは、女性メンバーは平均的に社会的敏感性が高かったという点です。これらの結果は、グループ内での相互作用のあり方や、相手を理解する能力が、集団の知的パフォーマンスに重要な影響を与えることを示しています。
集団知性の科学の広がりとさらなる可能性
この集団知能(c)の存在は、その後の多くの研究でも確認されています。22の研究、5279名、1356グループを対象としたメタ分析では、集団知能要因がグループの協働能力を予測する強力な指標であり、個々のメンバーのスキルよりも、グループの協働プロセスの方がCI(集団知能)の予測において重要であることが支持されました。社会的知覚能力の重要性も再確認され、集団知能とToMの関連性もより確実なものとなりました。
出典
- Riedl, C., Kim, Y. J., Gupta, P., Malone, T. W., & Woolley, A. W. (2021). Quantifying collective intelligence in human groups. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(21), e2005737118.
https://doi.org/10.1073/pnas.2005737118
さらに、心を読む力(ToM)はテキストベースでやり取りするオンライングループでも対面グループと同程度に集団知能と関連することが分かりました。つまり、ToMは単に相手の表情を見て心を読み取る能力ではなく、テキストなど多様なコミュニケーション手段を通じて発揮される能力であり、集団知性に重要な役割を果たすことが示されています。
出典
- Engel, D., Woolley, A. W., Jing, L. X., Chabris, C. F., & Malone, T. W. (2014). Reading the mind in the eyes or reading between the lines? Theory of mind predicts collective intelligence equally well online and face-to-face. PloS one, 9(12), e115212.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115212
AIの可能性への示唆
このように、集団知性の科学は、私たちがどう相互作用するか、またその過程で相手の心を理解する能力がいかに重要かを明らかにしています。そして、お互いをより深く理解できる仕組みづくりを通じて、集団知性をさらに向上させる道筋も見えてきています。
こうした知見を踏まえて、人工知能の可能性を考えてみましょう。
前回の記事で触れたように、AIは人間と相互作用する新しい知性として急速に発展しています。増加する相互作用はAIと人間の相互作用だけではありません。AI同士の協働や、人間同士の相互作用を仲介するなど、AIを通じた相互作用は急速に増加しています。このようにAIの活用により急増する相互作用の中で集団知性が生まれ、それをうまく活用できれば、これまで想像もつかなかったことが実現できるかもしれません。ここで重要なのは、集団知性の向上において相手の心を読み取る能力が鍵となることです。
では、AIには心を読む能力(ToM)があるのでしょうか?
次回は、AIのToM能力に関する興味深い研究成果をご紹介したいと思います。
フロー理論に基づくサーベイ、コーチングサービスはこちら↓