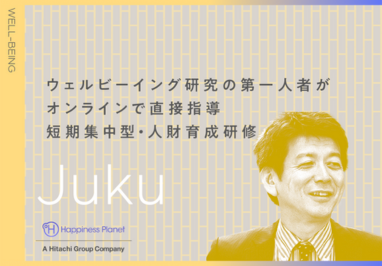「夜、ベッドに入っても目が冴えて眠れない」「朝、スッキリ起きられず1日がぼんやり始まる」。
そんな日々が続いていませんか?
厚労省の調査によると、日本人の5人に1人は「不眠」に何らかの悩みを抱えています。
睡眠不足は、仕事のパフォーマンスや人間関係、さらにはメンタルヘルスにも深刻な影響を与えるにも関わらず、「眠れないけど我慢してる」という方が多いのが現状です。
とはいえ、「忙しくて病院に行く時間なんてない」「薬には頼りたくない」といったジレンマもあるのではないでしょうか。
そんな中、注目を集めているのがデジタル療法(Digital Therapeutics)です。
今回は、11万人超の不眠患者データをもとにデジタル療法の効果を統合分析した論文をもとに、「どれくらい効くの?」「やる価値あるの?」という疑問に答えていきます。
出典
- Li, C., Luo, Q. & Wu, H. Digital therapeutics for insomnia: an umbrella review and meta-meta-analysis. npj Digit. Med. 8, 554 (2025). https://doi.org/10.1038/s41746-025-01946-y
実験概要:何をどのように調べたのか?
世界中の不眠症に関する信頼性の高い研究を集めて分析した「研究のまとめ(システマティックレビュー)」をさらに統合した、いわば「研究の研究」とも言える総合分析(アンブレラレビュー&メタ・メタ解析)を行いました。
対象者は延べ118,970人。主に不眠症を抱える成人を対象に、以下のような「デジタル療法」の効果が検証されました。
デジタル療法の例:
- dCBT-I(デジタル認知行動療法):スマホやPCで提供される睡眠改善プログラム
- オンライン睡眠指導・教育
- バーチャルコーチや睡眠アプリ
- ウェアラブルデバイスによる睡眠モニタリングとフィードバック
いずれも「薬に頼らず、習慣を変える」ことを目的に設計されています。
主な結果:どれくらい不眠が改善したのか?
◆ 不眠の重症度(ISIスコア)の改善
- 全体の効果:SMD = −0.42(p<0.01) → 軽〜中程度の改善
- 3か月後の効果:SMD = −0.69(p<0.01) → 中程度以上の改善
- → 時間が経つほど効果が高まる傾向が見られました。
◆ 睡眠の各指標に与えた効果
| 指標 | 効果の大きさ(SMD) | 結果の意味 |
|---|---|---|
| 睡眠の質(SQ) | +0.51 | 明確に向上 |
| 入眠までの時間(SOL) | −0.33 | 寝つきが早くなる |
| 中途覚醒時間(WASO) | −0.34 | 夜中に起きづらくなる |
| 総睡眠時間(TST) | +0.19 | 増えるが控えめな効果 |
補足的な気づき:どんな使い方をすれば効果が上がる?
1. セラピストのサポートがあるとさらに効果大
- セラピストがつく場合:SMD = −1.05
- セラピストなし:SMD = −0.84
→ やり取りがあることでモチベーションが維持され、実行率が高まると考えられます。
2. 「続けること」がカギ
- 使い始めよりも3か月後の方が効果が高い
→ アプリやプログラムは、最低でも12週間は使ってみるのがよさそうです。
3. 対面治療との比較
- 対照群が「何もしない」場合よりも圧倒的に効果あり
- 一方で、対面CBTと比べると効果はやや劣る
→ 「対面がベストだが、現実的にはデジタル療法も十分使える」と考えられます。
会社員にとっての実践ポイント
この研究から得られるヒントは次の3つです。
- 「短期より長期」で効いてくる
アプリを2〜3週間でやめてしまうのはもったいない。3か月以上続けることで効果が高まります。 - 必要に応じて専門家のサポートを併用
デジタル療法は単独でも有効ですが、セラピストによるガイドがあると効果はさらに大きくなります。 - 睡眠の「質」を重視する
総睡眠時間が長くならなくても、入眠の早さや中途覚醒の少なさが改善されることで、日中の集中力は大きく向上します。

まとめ:デジタル療法は「続けやすい睡眠改善法」
- エビデンスは十分にある:118,000人以上のデータで実証
- 短期より長期で効果が強い:最低3か月は続ける
- セラピスト併用で効果UP
- 睡眠の量より質を重視
忙しい会社員にとって、病院に通う時間がなくてもスマホ一つで始められるデジタル療法は、睡眠改善の大きな味方になり得ます。
「寝不足で仕事のパフォーマンスが落ちている」と感じる方は、まずは信頼できるアプリやオンラインプログラムを試してみてはいかがでしょうか。
もっと深く学び、実践したい方へ
このコラムでご紹介したような知見を、第一線の研究者と共に深く学べる研修を開催しています。
講師は、フロー理論や心の資本など、国内外の研究者と共同研究を行ってきた矢野和男が務めます。バラバラに見える心理学的知見を、ウェルビーイングという軸で整理し直すことで、職場や組織に新たな視点が生まれます。
そして、プログラムで得た知見や参加者同士のワークショップを通じて、組織のウェルビーイングリーダーとしてのマインドセットを磨いていただきます。学びを現場へと活かし、組織内のウェルビーイング実践にご興味のある方は、ぜひ参加をご検討ください。