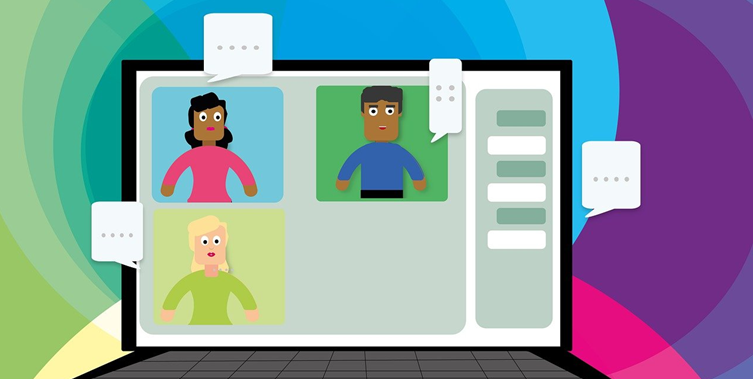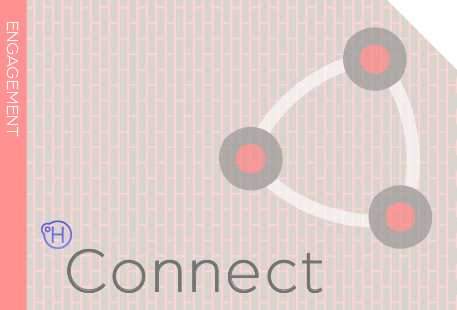「最近、部下がどれくらい仕事に前向きに取り組めているのか分からない…」
「忙しい現場で、チームのメンバーが負担を感じていないか?」
「チームの様子が何となくぎくしゃくしているのを感じるが、気のせいかな?」
リモートワークが広がって以降、多くのマネジャーやリーダーが抱えている共通の悩みです。顔を合わせていれば、ちょっとした雑談や仕草から「元気そうだな」「少し疲れているな」と察することができました。しかしオンライン中心になると、その感覚的な情報が一気に減ってしまいます
社員のワーク・エンゲージメント――つまり「活力・献身・没頭」といった前向きな心理状態を評価する一般的な方法として、社員アンケートを取る方法があります。しかしながら、回答自体が社員の手間となったり、また同じアンケートを繰り返し利用することで、設問とスコアの関係性を推測し意図的に高得点を得る「アンケート・ハック」が可能となる恐れがあります。
では、どうすれば社員のワーク・エンゲージメント・レベル(WEL)を、無理なく、しかも正確に把握できるのでしょうか。
コラムでは2回にわたって従業員のエンゲージメントレベルを、SlackやTeamsといった、 オンラインコミュニケーションツール のデータから推し量る試みについて、紹介します。
今回はSlackのメッセージデータから 心理的安全性 を推測する研究をとりあげます。
出典
- Sharon A Ferguson, Georgia Van De Zande, Alison Olechowski : No Risk, No Reward: Towards An Automated Measure of Psychological Safety from Online Communication https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613905.3650923
組織内のコミュニケーションを促進する立場にある方にとって、心理的安全性は避けて通れないテーマです。心理的安全性は、チームの中で「自分の考えや疑問を安心して表明できる」状態を指し、WELにも大きく影響する指標といえます。Googleの研究でも、高業績チームの決定的な要素として注目されました。しかし、その測定方法はこれまで「アンケート」に頼るしかなく、リアルタイムでの把握は難しいものでした。
リモートやハイブリッドで働くチームが増える今、チャットツールのデータから“安心感の度合い”を読み解けるとしたら、とても心強いと思いませんか?
研究のアプローチ
研究は、アメリカの大学で活動した2つの学生デザインチームを対象としています。一方は心理的安全性が高く、もう一方は低いと調査票で評価されたチームです。両チームのSlackメッセージ(数か月で約13,000件、学生+スタッフ約40名)を分析し、心理的安全性がどのように表れるのかを探りました。
アプローチは2種類あります。
- 定量分析:返信数や絵文字の利用回数、@メンションなどを数値化して比較。
- 定性分析:具体的なメッセージの内容を読み取り、使われ方の違いを観察。
こうすることで、「数の違い」と「文脈の違い」の両面から心理的安全性をとらえようとしました。
分析方法
心理的安全性を示す行動は、大きく4つのカテゴリに整理されます。
- 発言行動:ミスを認める、助けを求める、批判を伝えるなど。
- 支援行動:同意や感謝を表す、肯定的に反応するなど。
- 学習行動:改善案を出す、意見を求める、提案にフィードバックするなど。
- 親密性行動:冗談や絵文字を使い、フランクな関係性を示すこと。
研究チームは、各カテゴリに対応する「キーワードリスト」を作成し、Slackのメッセージを自動検索しました。たとえば「sorry」「help」「disagree」といった言葉が発言行動に関連づけられます。また、返信数や絵文字リアクション数なども合わせて測定しました。
ただし、単純にキーワードを拾うだけでは不十分です。そこで、実際の会話を精読して「どういう文脈でその言葉が使われているのか」を見ていきました。
定量分析の結果
数値として顕著だったのは以下の点です。
- 返信数:高PS(Pshochological Safety:心理的安全性)チームの方が、1つの発言に対して多くの返信がつきやすかった。(1件でも返信が付く割合は高PSチームでは18%であるのに対して低PSは12%)
- 絵文字リアクション:高PSチームは絵文字リアクションを豊富に使っており、特にカスタム絵文字(メンバーの写真など)も多かった。
- 投稿の均等性:高PSチームは発言がメンバー全体に均等に分布しており、特定の人に偏っていなかった。(総メッセージ数に対する標準偏差は高PSチームは3.4%であったのに対し、低PSチームでは6.4%)
- @メンション:高PSチームは他のメンバーを呼びかける回数がやや多かった。
一方で、単純なキーワードの出現率には大きな差が見られませんでした。つまり「何を言ったか」よりも「どう反応し合ったか」「どんな形で交流しているか」が、心理的安全性を映し出していると考えられます。
定性分析の観察
より深くメッセージを読むと、違いが浮き彫りになりました。
- 発言行動
高PSチームでは、自分の作業内容を共有したうえで「ここが分からないから助けて」と助けを求める姿勢が多く見られました。一方で低PSチームでは「分からない」と短く答えるだけのケースが目立ちました。
- 批判の仕方
高PSチームは「この回路のピン数で本当に動かせる?」といった具体的・建設的な批判が中心。一方で低PSチームは「テストがゼロだ」「進む道がない」など、抽象的で否定的な批判が多く、個人攻撃に受け取られやすいものでした。
- 支援行動
高PSチームは「〇〇さんが昨日片付けを手伝ってくれて助かった!」のように、個人と具体的な行動を称える感謝が多く、低PSチームは「みんなよくやった!」といった漠然とした褒め言葉が目立ちました。
- 親密性行動
両チームとも冗談や絵文字は多用していましたが、使い方に違いがありました。高PSチームは支援や共感を示すために絵文字を使用しました。一方で低PSチームは注意を引く目的で「⚠️」などを多用し、緊張感のある雰囲気を感じさせました。
研究が示すこと
この研究から得られる重要な示唆は、心理的安全性は「言葉そのもの」よりも「関わり方や反応の仕方」に色濃く現れるということです。
- 返信が活発かどうか
- 絵文字がフレンドリーに使われているか
- 発言が一部の人に偏らず、チーム全体で分担されているか
こうした指標は、アンケートに頼らずに心理的安全性を推し量る有望な手がかりとなりえます。
一方で、この研究は2チームという限られた事例に基づいており、あくまで探索的な成果です。今後はより多くのチームデータで検証し、AIや高度な言語解析手法を用いることで、さらに精度の高いモデルが開発されると期待されています。
まとめ
心理的安全性は、チームが力を発揮するために欠かせない要素ですが、従来はアンケートでしか測れませんでした。この研究は、普段のSlackメッセージに隠れたシグナルから、自動的に心理的安全性を把握できる可能性を示しています。
「ありがとう」の伝え方や、絵文字の選び方、批判の仕方、日々のちょっとしたやり取りから、チームが安心して挑戦できているかを読み取ることができるのです。
もしあなたがチームを率いる立場なら、次にSlackを開いたとき、単なるスタンプのやり取りに見える行動が、実はチームの心理的安全性を映す“バロメーター”かもしれません。