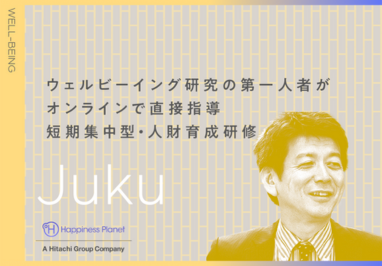仕事のストレスがたまっているとき、「運動した方がいい」とはよく聞きます。でも、いざ始めても続かない。楽しくない。そもそも何から始めればいいのか分からない——。そんな悩みを抱える会社員は少なくないはずです。
実は、最近発表された研究で「性格によって、どんな運動が楽しく感じられるか」「どれくらいストレス軽減効果を得られるか」がわかってきました。つまり、“自分の性格に合った運動”を選べば、無理せず続けられて、心身にもより良い影響を与える可能性があるというのです。
この記事では、ロンドン大学の研究チームが実施した最新の実験結果をもとに、「あなたに合った運動タイプ」と「効果的な続け方」のヒントをお届けします。
出典
- 出典:Ronca, F., Tari, B., Xu, C., & Burgess, P. W. (2025). Personality traits can predict which exercise intensities we enjoy most, and the magnitude of stress reduction experienced following a training program. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1587472
実験概要:性格と運動の「相性」を科学的に検証
研究目的:
- 性格によって運動の楽しさ・継続・効果に違いが出るのか?
- 特にストレス軽減効果にどんな差があるのか?
被験者:
- 一般市民132名(女性56名・男性76名、平均年齢38歳)
- 職業:大学生、医療従事者、警察官など多様な背景
- BMI・年齢・性別・体力(VO₂peak)をもとに2グループに分けた
実験内容:
- 介入群(78名):8週間のホームトレーニング(自転車+筋トレ)
- 対照群(54名):軽いストレッチのみ
性格測定:
- ビッグファイブ性格特性(外向性・誠実性・神経症傾向・協調性・開放性)
- ストレス測定(PSS-10尺度)
運動メニューの例:
- 低強度ライド(HRゾーン2で50分)
- 高強度インターバル(HIIT、2分×4本の全力走)
- 筋トレ(スクワット・ランジなど自重で3セット)
- VO₂peakテスト(運動耐性の限界を測る)
主な結果と発見:性格によって異なる「運動の楽しさ」と効果
1. 性格と“もともとの体力”の関係(ベースライン比較)
外向性が高い人は、VO₂peak(最大酸素摂取量)が高い傾向にあり、心肺機能が高い傾向にありました。逆に、神経症傾向が高い人は、高い心拍数から元の心拍数に戻るまでに時間がかかり、心拍機能が低い傾向にありました。誠実性が高い人ほど、運動習慣を身に着けている傾向にあり、体脂肪、筋力共に良好な傾向にありました。
| 測定項目 | 外向性が高い人 | 誠実性が高い人 | 神経症傾向が高い人 |
|---|---|---|---|
| VO₂peak(最大酸素摂取量) | 高い(平均41.3 ml/kg/min) | – | – |
| 心拍回復(HRR) | – | – | 低い(2分後の回復が遅い) |
| 筋力(腕立て回数) | – | 高い(1分間平均31回) | – |
| 体脂肪率 | – | 低い(男性平均19.3%、女性平均25.9%) | – |
| 運動習慣(週あたり運動時間) | – | 多い(平均6.3時間) | – |
2. 性格と「どの運動が楽しかったか」
外向性が高い人ほど、HIIT(高強度インターバルトレーニング)やVO₂maxテストのような激しい運動を楽しむ傾向がありました。心拍数を上げて汗をかくようなセッションがむしろ“気持ちいい”と感じやすいようです。
一方で、神経症傾向が高い人は「軽めで一人でできる運動(ストレッチやゆるいサイクリング)」を好む傾向がありました。特に、人に見られていない状況の方が安心して取り組めるようです。
| 運動種目 | 楽しんだ性格タイプ | 傾向 |
|---|---|---|
| VO₂peakテスト・HIIT | 外向性が高い人 | 強い刺激を楽しむ |
| 低強度ライド | 協調性が高い人 | 穏やかな運動を好む |
| ストレッチ・軽い運動 | 神経症傾向が高い人 | 自分のペースを好む |
| 高強度運動(HIITなど) | 開放性が高い人は逆に楽しさが低下 | 体への過敏さ? |

3. 性格と“運動のストレス軽減効果”の関係
PSS-10という尺度でストレスの変化を測定。
- 神経症傾向が高い人:
ストレスが大きく低下(P = 0.003、効果量 R² = 0.15)
→ 運動開始前はストレスが最も高かったが、最も改善も大きかった - 神経症傾向が低い人:
ストレス低下は小さめ
興味深いのは、神経症傾向が高いタイプの人こそ、運動によるストレス軽減効果が最も大きかった点です。「自分に合った方法で運動すれば、精神的な恩恵は最大化する」と言えそうです。
4. 継続率と自己管理への影響
神経症傾向が高いタイプの人は、運動中に心拍数の記録をしない傾向にありました。心拍数に左右されず、自分のペースで運動することを好む傾向にあるようです。
また、性格特性によって、再テストの参加率にも差が出ました。
| 性格特性 | 傾向 |
|---|---|
| 神経症傾向が高い | 心拍数の記録をしない傾向(オッズ比=0.73) |
| 外向性が高い | 最後のテスト(ポスト測定)に来ない傾向(オッズ比=0.70) |
| 開放性が高い | 継続参加しやすい(オッズ比=1.42) |
まとめ:性格を知ることで「運動の失敗」を防げる
今回の研究が教えてくれるのは、「性格に合った運動法を選ぶことが、継続と効果のカギになる」ということです。
忙しい日々の中でも、無理なく、楽しく、そして心のケアにもなる運動を取り入れていく。そのための第一歩として、「自分はどんな性格で、どんな運動が向いているか?」を一度考えてみてはいかがでしょうか。
| 性格タイプ | おすすめ運動 | 注意点 |
|---|---|---|
| 外向型 | HIIT・グループレッスン | 飽きやすさに注意 |
| 神経質型 | ストレッチ・ゆるい自転車 | 他人の目がない環境が◎ |
| 誠実型 | ルーティン運動・筋トレ | 楽しさより「目標重視」 |
| 開放型 | 新しい運動への好奇心は強いが、高強度は苦手 | フォーカスしすぎ注意 |
もっと深く学び、実践したい方へ
このコラムでご紹介したような知見を、第一線の研究者と共に深く学べる研修を開催しています。
講師は、フロー理論や心の資本など、国内外の研究者と共同研究を行ってきた矢野和男が務めます。バラバラに見える心理学的知見を、ウェルビーイングという軸で整理し直すことで、職場や組織に新たな視点が生まれます。
そして、プログラムで得た知見や参加者同士のワークショップを通じて、組織のウェルビーイングリーダーとしてのマインドセットを磨いていただきます。学びを現場へと活かし、組織内のウェルビーイング実践にご興味のある方は、ぜひ参加をご検討ください。